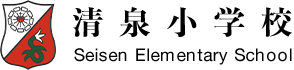三浦半島の自然にいだかれて
三浦自然教室は、京浜急行 三浦海岸駅から北東に徒歩15分のところにあります。
約1万坪という広大な自然をそのまま教室として自然教育を行っています。
日常の教科学習では到底得られない心身を一丸とする生活体験を通して、強い意志力、たくましい身体、自然愛、人間愛、正しい勤労観をもつ豊かな人間性を育みます。
施設紹介


 いずみ広場
いずみ広場
昔はクローバーが生えるクローバー広場でしたが、2008年に後援会の方々によって、芝生が植えられ、清泉小学校の「泉」を取って、いずみ広場と名付けられました。
ここにはダンゴムシやバッタやカマキリ、モグラなど、色々な生き物がいます。
活動例
秋の集い(運動会)、竹馬、かけっこ、鬼ごっこ、虫捕りなど


 どんぐり山
どんぐり山
コナラやマテバシイなどのどんぐりの木が密生するこのエリアでは、アスレチックや階段を使った運動ができます。
秋にはどんぐりがたくさん落ちています。
活動例
アスレチック遊び、秘密基地作りなど


 きぼうの道
きぼうの道
水田や子どもの広場を見ながら、みかん園までつづく、木々の美しい小道で、ミズキ、サザンカ、クサギ、クワ、ハンノキ、アケビやカキの木などがトンネルのようにきれいにならんでいます。
この道は卒業生の方々によって作られました。


 水田
水田
5年生が毎年、6月にもち米を田植えし、草取りなどのお世話や10月の稲かりを体験しています。
ここで育てたもち米は、おもちつきをして頂いたり、紅白餅にして新一年生にプレゼントしたりしています。
また、春には黄色のキツネノボタン、秋には赤色のミゾソバの花が見られ、カエルやトンボなどの生き物と触れ合うこともできます。
活動例
稲作、生き物探し


 子どもの広場
子どもの広場
あたりには、たくさんの草木があり、夏はとても涼しい広場です。
クリの木やアンズの木もあり、秋にはたくさんの実をつけています。
活動例
かくれんぼ、秘密基地作りなど


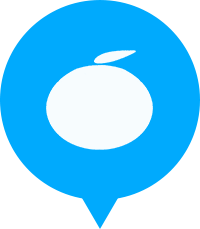 みかん園
みかん園
100本ほどのみかんの木があり、春には、白い花が咲きとてもよい香りがします。
夏には小さい実がつきはじめ、秋にはオレンジ色のおいしいみかんがなります。
冬になるとみんなでみかん狩りを楽しみます。
活動例
みかん狩り、宝探し


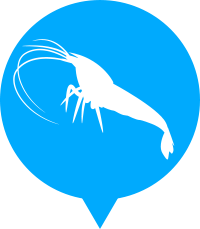 ひょうたん池
ひょうたん池
ひょうたんのような形をしているので、この名前がつきました。
ここにはヌマエビ、カエル、アメンボ、小魚、カニ、ドジョウなどの生き物がいます。
冬には、池の表面に氷がはる様子を見ることもできます。
活動例
生き物探し(ヌマエビ取り)


 湿地
湿地
ドジョウやザリガニ、カエルなどの多くの生き物がいます。
活動例
ザリガニ釣り


 まよいの森
まよいの森
緑ゆたかな広い森の中にいくつも道がのびていて、まるで迷路のように迷ってしまうほど広いことから、「まよいの森」と名付けられました。
北向きの斜面には、ハゼ、カラスザンショ、エノキ、ハリギリなどの木があり、春にはタケノコが生え、秋にはきれいな紅葉が楽しめます。
活動例
探検ごっこ、秘密基地作り、かくれんぼ


 化石広場
化石広場
整地をしたときにトウキョウホタテなどの化石が発見されたことから、この名前が付きました。
風通しも良く屋根がついているため、雨でも活動することができます。
活動例
火おこし、七輪調理(焼き芋、サトイモ焼き、カレー作りなど)、カートンドック、もちつきなど


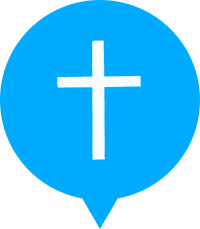 聖ラファエラ・マリア館
聖ラファエラ・マリア館
1977年に建てられ、創立者聖ラファエラ・マリア様を記念して「聖ラファエラ・マリア館」と名付けられました。
自然教室の真ん中あたりの高台(標高30m)に位置するこの4階建ての建物には、1学年が全員座れるだけの椅子と机が置いてあるスカイルームや、合宿の時に寝袋を敷いて寝るコルクの部屋、お風呂場、調理室、保健室などがあります。
活動例
合宿の時の宿泊、食事、顕微鏡を使った観察、雨の日のレクリエーションなど


 畑
畑
1学年2種類の作物や、全学年で収穫する大根など季節にあわせて多くの作物を育てることができる広い畑で、自然のありがたさ、神様のお恵みを一番感じられる場所です。
ここからまよいの森へ続く道もあります。
収穫物
エダマメ、トウモロコシ、ラディッシュ、インゲン、カブ、ニンジン、サトイモ、サツマイモ、小麦、ソラマメ、ブロッコリー、カリフラワー、大根、ジャガイモなど。


 鐘楼
鐘楼
鐘楼は1979年3月に作られました。鐘は、戦争が終わって横須賀に清泉が作られた時、平和の祈りを込めてアメリカから贈られたものです。今でも行事の時などに使われ、美しい音を響かせています。